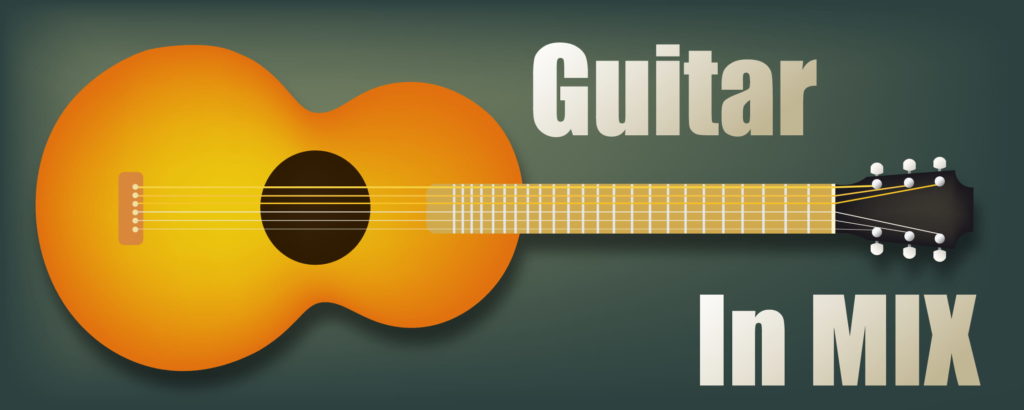
Mixはクリエイティヴな作業であり、決まった正解というものがありません。必ず上手くいくセッティングはないということです。なぜか。楽曲の内容に合わせたミックスをしなければならない、というだけでなく、
同じ楽器であっても、他の楽器との関わり合いで役割が異なってくるので、ミックスにおける処理も変わる
からです。
例えば、アコギをミックスの中でどう扱うか、というのは最も難しい課題のひとつです。そんなアコギの処理を例にミックスという作業について考えていきます。
ミックスに方程式はない?
よくMixにおいては、こうすれば必ず上手くいくという公式のようなものはない、ということが言われます。
曲、音楽のスタイル、ジャンルや楽器編成によって、最適なやり方が変わるからです。つまり例えば、じゃあベースをこのくらい、ギターをこのぐらいにして、後はボーカルにコンプレッサーをこれくらいかけて、あの有名なリヴァーブをかければ全てがうまくいく!、とはなりません。
定番のプラグインやスタジオに伝わる伝統的な手法、機材の使い方というのもあるにはあるのですが、曲ごとの調整は必ず必要です。
作業内容を数量的に表すことができないというのが、ミックスを理解する上で大きな壁の1つです。 最終的には自分がいいと思える音にすればいいのですが、それが難しい。独りよがりな音になってはだめな訳ですので。
最終的には、経験によって作品性と客観性のバランスに優れたミックスが出来るようになるので、だからこそミックス・エンジニアという専門のエンジニアが重要になってくるわけです。
音楽における”状況”の違い
状況によって音の処理が変わるとはどういうことか?まず2種類の状況を想定してみたいと思います。
- 弾き語りにおける、アコギのサウンド。
- バンドサウンド内における、アコギのサウンド。
まず、この2つの大きな違いは当然、その編成における楽器の数です。弾き語りによるサウンドは、今回は1人だけで、アコースティックギターとボーカルの2つの楽器しか存在しません。
それに対して、二つ目は一般的なバンドを想定し、エレキギター、アコースティックギター、ベース、キーボードとドラムという編成とします。
この2つの楽器編成において、アコースティックギターが、それぞれどのような役割を担うのか? 同じ楽器なのに、その役割はかなり異なるものとなります。
弾き語りでのアコギ
まず、弾き語りの場合を考えると、アコギの役割は和音だけでなく、リズムとベース(低音)といった数多くの役割を担うことになります。
つまり、ジャカジャカというパーカッション成分、歌メロを包み込むコード成分、そして和音の基盤を担う低音、といったアコギという楽器のすべての要素が必要になります。
バンドの中のアコギ
逆に、バンド編成におけるアコギを考えると、バンドにおいてはベースとバスドラムといった低音を主とする楽器があるわけです。それだけでなく和音を奏でる楽器がほかにも多くあります。(ここではキーボードとエレキギター)単純にアコギ以外の楽器が多い、という状況です。
低音はそれだけでも、多くのエネルギーを持っているので、過剰な低音はミックスを崩壊させます。(かといって少なすぎてもダメですが。)
つまり、この状況において、アコースティックギターにおける低音成分とは、多くの場合不要なものであり、ベースやバスドラとぶつかるのを防ぐために、カットしてしまう方が良いと考えられます。
それぞれの処理の方向性
こうして二つの状況におけるアコギの役割の差を考えると、まず弾き語りにおいては、録り方にもよりますが、低音成分をブーストするような処理が考えられます。ベースの代わりを務めるからです。
バンド編成においてはバスドラムやベースギターを邪魔しないよう低域成分をカットし、かつほかのギターや、ピアノと和音がぶつかり合わないように調整し、どちらかというと全体を包み込むようなジャカジャカと、軽ろやさと広がりのあるサウンドになるような処理をした方が良い、というような判断になります。
これはあくまで一般論として、こうした方がおそらく上手くいくだろうというものです。すべての状況においてこうすればよい、というものではないですが、ひとつの基準ではあります。とにかく音楽的状況から判断してEQやコンプなどでの処理が変わるのは、こうした判断によるということです。
全てを併せて1になるように
まとめると曲をしっかりと聴いて理解した上で、アレンジ、各楽器などの役割を考えて、各々音造りをしていこう!ということになります。絶対的な方法論はないけど、他の楽器やトラックとの関係性から、その楽器の役割を考え、それにあった調整や音作りをしていく、ということです。
全ての音がなったときに100%になるようにする、ということであり、分母が増えても、全体は“1”であるべきです。本来であるなら、生楽器はみんな100%であるべきですが、オーディオ的限界のために例えば、ヴォーカル0.5 アコギ0.5というようなバランスに音造りをしなければいけないのです。それが120%とか150%になってしまうと、崩壊してしまいます。
というわけで、mixにおける分かりにくい部分をアコギを題材に説明してみました。
