音楽は時間に沿って変化し、進展していくモノ。前後関係における、差異や変化が音楽にドラマ性を生みます。サウンド面からも、ストーリーを作っていく、というレンジ・マネジメントについての提案です。
レンジ・マネジメントとは
音の大きさを始めとして、音楽には様々な幅(レンジ、Range)が存在します。ミックス、ミキシングをする上で、それらを音楽のストーリーに合わせて、どうコントロールしていくかが重要になります。幅を管理しつつ、その中で適切な値を選ぶ、ということです。
ミックスは何より、バランスを取ることが大事ですが、難しいのは音楽は常に変化する流動的な表現、存在、現象であり、それに応じた、動的な対応が求められるということです。”幅”というのはどの程度の範囲で変化するかの幅です。広すぎても、特にオーディオにおいては収集がつかなくなりますし、狭すぎてもつまらなくなります。
音楽のコンテキストを適切に判断し、その幅を管理し、そして全体を通しての音楽的なストーリーを補強するために、その幅の中で揺れ動かすことでサウンドに演出を加えます。その幅の管理、コントロールをレンジ・マネジメントと命名したいと思います。
音楽に潜む、様々な『幅』
では、一体どんな幅があるのか。
- 音の大小(小さい、大きい、静か、うるさい)
- 横の拡がり、パノラマ(狭い、広い)
- 周波数帯域(狭い、広い、薄い、濃い)
- 奥行き(近い、遠い)
- 音色(柔らかい、硬い、暗い、明るい)
これらの要素が、破綻しない程度に揺れ動くと、それは音楽的なミックス、サウンドになります。もちろん、どの程度の幅か、どう変化すべきかは音楽スタイルによっても基準が異なります。
これらに変化がないと、人は慣れる動物なので、すぐに飽きてしまいます。例えば、同じフレーズの繰り返しでも、音色に変化があれば、それは進展感が加わります。強弱の変化が加わるだけでも、同様です。しかし、まったく変化のない5音のフレーズはそれだけを10回も聞いたら、もうそれは苦痛でしかない。
実際の音楽では、これらの要素に加えて、楽曲そのものの音楽的内容が絡み合うので、複雑な関係性になります。なので、これらの要素を考える場合は、要素ごとに切り分ける必要がありますし、曲の構成の節目をひとつの単位として、見ていかねばなりません。各項目ごとに、その特徴と実際のミックスでどう考えていくかをまとめていきます。
音の大きさ
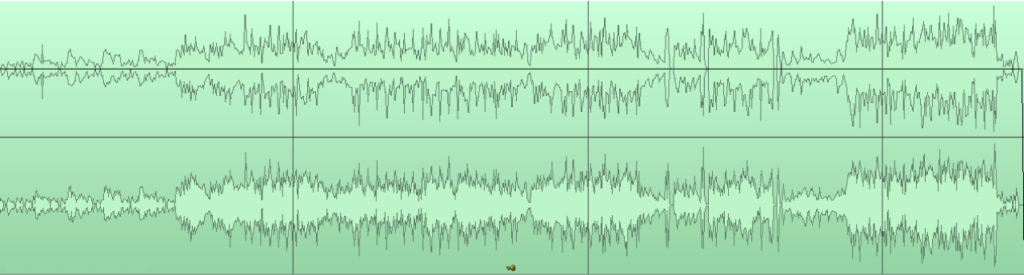
ダイナミクス・レンジとも言いますが、音の大きさの変化が与える音楽的印象は大きいです。
小さい音は静寂さ、弱さ、孤独
大きい音は強さ、雄大さ、厚み、など
小さい音から大きい音への変化は始まり、そして盛り上がり、という印象を与えますし、大きい音から小さい音への変化は、落ち着き、あるいは停滞の印象を与えるかもしれません。
ミックスにおいては、おそらく一番音が大きくなる、つまりRMSが最大になるのは最後のサビです。最後の盛り上がりになります。それに対して、イントロの音量、Aメロの音量が相対的に小さく、ふさわしい音量に調整する必要があります。
曲を通して、音量がどう変化していくかを管理していくということになります。最近ですと、リミッター、マキシマイザーで音量をあげるので、波形はペッタンコになってしまいますが、すくなくともRMS(いわゆる音圧)の変化は重要です。例えば、静かなところで、-15dBFS、普通の所で-11dB ~ -8dBぐらいの範囲、盛り上がるところで-8 dB ~ -6dB位の範囲に収める、みたいなことになります。
横の拡がり
ステレオ・オーディオであれば、二本のスピーカーによって、左右の広がりが表現されます。ミックス的には重要なものは真ん中に、それほどではないモノや周波数的に軽いものを左右にちりばめるのが定石になっていますが、時間的な変化も重要です。
曲の盛り上がりに応じて左右に拡がる、というのは、リスナーに好印象を与えるようです。逆に曲を通して広がりぱなしだと、拡がってはいても、退屈な印象を与えます。やはり程よく拡げつつも、曲の節目ごとに変化させていくことが重要です。
また、トラック単位ではパンニングを動かす、というテクニックもあります。これも音に動きを与える効果が期待できます。
周波数帯域、密度
Frequency Range フリクエンシー・レンジです。周波数というのは、要するに音の高低です。一秒間にたくさん振動すれば高い音、少なく振動すれば低い音、などという細かい話はここでは省略します。要するに、低い音、高い音がどの範囲まで拡がっているか、ということです。
ここでは、音の密度も扱いたいと思います。どのくらいたくさんの音が同時になっているか、ということで、ミックス全体がその時点で、どのくらいの周波数を含んでいるのか、ということです。少ない音数だと、薄い、静かな印象で、たくさんの音が鳴れば、厚く、騒々しい、白熱した印象になります。
その曲で使われる、アレンジ上の全ての楽器が常に鳴っている、というのは盛り上がっている印象は最初だけで、あまりに長く続くと慣れて退屈になってしまいます。曲のセクション毎に鳴らす楽器の数を決める、というのは編曲段階の判断ではありますが、ミックス時点でもこれを考慮して、時にはトラックをミュートすることもあり得ます。
やはり、密度、帯域共に最大になるのは、最後のサビであり、そこが一番盛り上がる場所です。当然、音量も最大になりますが、全ての楽器を鳴らす、というのはここぞというところでしか使うべきではないということです。鳴る音の帯域、密度をコントロールすることで、曲のセクション毎の役割、盛り上がる場所なのか、あるいは少し休憩する場所(ブレイク)なのかを明確にします。
奥行き
これはあまり変化させないかもしれません。しかし、ある瞬間にリバーブを切ることで、面白い効果を得ることもできます。
生演奏重視以外の音楽スタイルによっては、奥行き、つまり、音の近さ、遠さを極端に変化させることで、あまり聴いたことのないサウンド効果を得られるかもしれません。ミックスにおける距離感についてという別個の記事をご覧ください。
左右の広がりではなく、奥行きもサウンドにおける空間感において重要です。
音色、トーン
おそらく一番分かりやすく、リスナーも意識的に聴く要素です。今までの要素はどちらかというと無意識的に聴く部分であり、もちろん重要なのですが、特に取り沙汰されない部分でもあります。
しかし、この音色の変化というのは、他の要素よりも楽曲とより密接に関係しあい、切り離せない要素になります。
音色の変化は、ダイレクトに音楽の印象に影響を与えます。クリーンギターから、ディストーションギターへの変化がわかり易いです、サビですよ!盛り上がりますよ!という印象を与えます。テクノ音楽で、シンセのフィルタが変化していくのは、弾かれるフレーズが同じでも、変化の印象を与えます。
まとめ!
以上の要素の変化、あるいはその幅をコントロールすることが、ミックスを単なる調整作業以上のものにする上で重要です。サウンドに生命観を与えます。
実際の音楽においては、これらの要素が複雑に、有機的に、そして流動的に絡み合いながら、音楽は進行していき、そのサウンドを形成します。
その幅を適切な範囲に収め、その中で曲の進行に合わせた具合を調整し、変化を付けていくことで、サウンドの面から、その曲が持つストーリーテリングを増幅させる、というマネジメントであり、演出についての内容でした。
